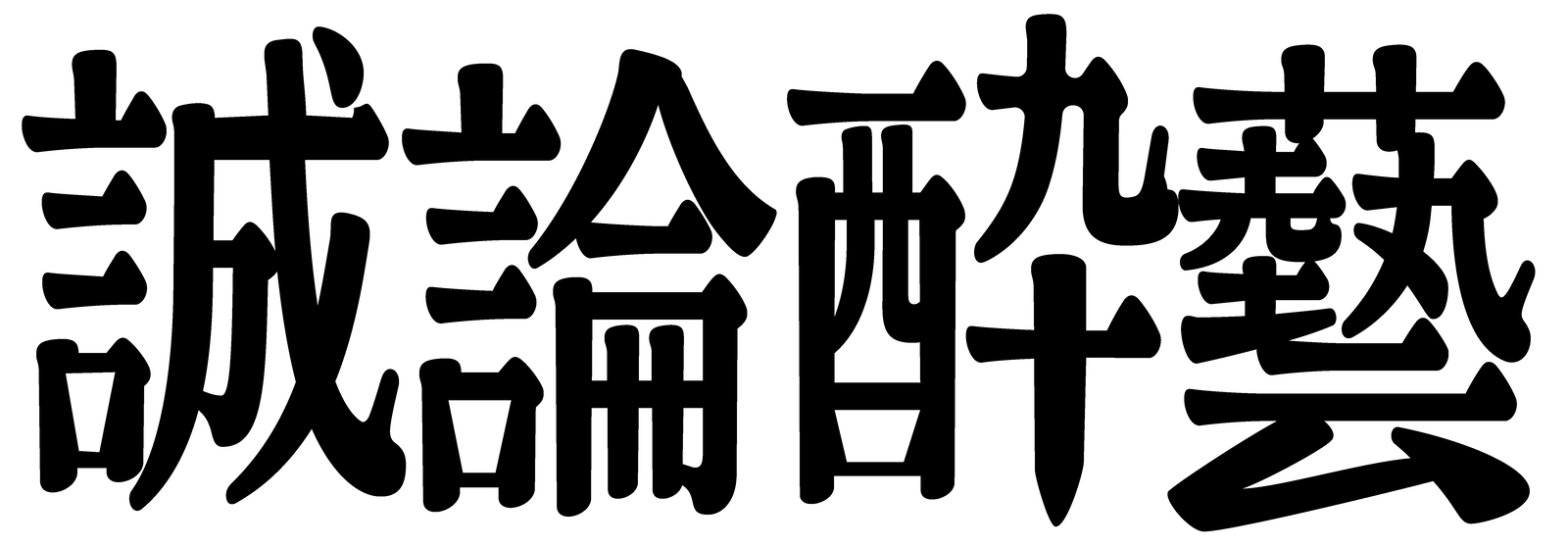2020年3月14日号。<新型コロナウイルス特措法可決 / 一九八二年、僕はエロ本の出版社に入った。 第四八回「坂道」:東良美季>

閑散としていた新宿ゴールデン街

中村京子さんと
<新型コロナウイルス特措法可決 / 一九八二年、僕はエロ本の出版社に入った。 第四八回「坂道」:東良美季>
おはようございます。ヨロンです。
昨夜は、おなじみの木村敬さんに誘われて新宿ゴールデン街に行きました。店は、今日もお送りするトーラさんの「僕エロ」にも登場していた中村京子さんの『中村酒店』。5人も入ればいっぱいになってしまうような、カウンターだけの狭い店です。
ゴールデン街は最近は観光スポットとなっていて、外国人、特に白人系が目立ち、真っ直ぐ歩くことができないほどでしたが、昨日はゴーストタウンのよう。繁盛している店はそこそこ客が入っているのですが、多くは閉店後かと思うほど閑散としていました。
新宿の街に出ても人は少ないのですが、その中でも若い人の比率が高い。感覚的なものですが、年配の人は夜飲み歩くことが激減し、家にじっとしていたくない若者が街に繰り出している印象です。
帰りに鶴見駅でJRから京急線に乗り換えると、駅の前でぴょんぴょん跳ねながら、歩いている女性を次々とナンパしている若い男性がいました。当然、女の子は無視して通り過ぎていきます。いつもなら、あまりしつこいとひとこと言ってやりたくなるのですが、どこの街も活気がなくなっているからか、妙に明るく微笑ましくさえ見えました。
国会で新型コロナウイルス特措法が可決されました。今日から施行されます。私はちょうど参議院の議員会館にいたので、リアルにこの瞬間に立ち会いました。
<新型コロナウイルス対策の特措法 成立 「緊急事態宣言」可能に>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012330031000.html
<新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に備え、総理大臣が「緊急事態宣言」を行い、都道府県知事が外出の自粛や学校の休校などの要請や指示を行うことを可能にする特別措置法案は、12日、衆議院を通過し、13日、参議院内閣委員会で質疑と採決が行われた結果、賛成多数で可決されました。
また委員会では衆議院内閣委員会と同じく、▽緊急事態宣言にあたっては、緊急でやむをえない場合を除き国会に事前に報告することや、▽その後の状況を適時、報告することなどを盛り込んだ付帯決議も賛成多数で可決されました。>
注目の「緊急事態宣言」は、建前上は専門家の意見を聞いて国会への事前報告を行うことになっていますが、実際には首相の一存で出すことができます。
野党は「付帯決議」というもので暴走させないように歯止めをかけましたが、これは法的拘束力を持ちません。また、付帯決議にも”緊急でやむをえない場合を除き”と入っているので、全国一斉休校のように思いつきで出して、あとで「これは緊急でやむをえない場合であった」と言えば済んでしまいます。
民主党政権で特措法を成立させたときには、まさか首相が法律を自由に解釈変更したり、省庁で公文書を改ざんされることは想定していなかったので、今回野党の一部の議員は抵抗しましたが、すでに国家の緊急事態ということで、圧倒的多数で可決されました。
アメリカではトランプ大統領が緊急事態宣言を出しました。日本でも今後の拡大次第では出される恐れもあります。
そもそも緊急事態宣言は、国家の危機と言える自体になったときに、国民の行動や権利を強制的に制限し感染拡大を抑え込むのが目的なので、的確に運用されれば問題ありません。しかし、そもそも「緊急事態」というものの定義が曖昧であるので、極端な話、収束に向けて遷移していても安倍さんが「今こそ緊急事態だ」と言えば、それは緊急事態なのです。期間も最長2年と決められていますが、緊急事態宣言後にそれを延長すると宣言すれば、そちらのほうが優先されます。つまり永遠に延ばすことも可能です。
そうは言っても、むやみに出してしまうと国民生活も経済も混乱し、国力は著しく低下します。国民は我慢を強いられ、ストレスが溜まっていき、倒産する企業も急激に増えていくでしょう。
現実問題として考えれば、緊急事態を宣言するとそれ以上のことはないので、政府からしたら最終兵器のような扱いになります。一部の野党が懸念しているような濫用ができない法律です。常識的に運用していけば効果は出せる。
今日の夕方、安倍首相が国民に向けて説明を行うそうですが、そこでは「慎重に判断していく」ということが言われるでしょう。
実際に緊急事態を宣言するとしたら、今月下旬。19日に専門家会議の判断が出て、それを受けてということになるでしょう。それまでに抑え込む傾向が見えると良いのですが、予断を許しません。
完全な抑え込みには半年や一年はかかるでしょうから、何度も言っているように全部まとめて制限をかけるのではなく、重症になりやすい高齢患者の早期発見治療に重点を起きながら、徐々に自粛を解除していく方向に持っていくべきです。
緊急事態宣言は、それを逆行させるので、出されるとしたらどのタイミングでどのような内容となるのか、注目する必要があります。
今朝の関東は寒く、横浜では冷たい雨が降っています。これも、春に向けてジャンプするためにしゃがみ込む瞬間だと思っています。
—– : —– : —– :
一九八二年、僕はエロ本の出版社に入った。 第四八回「坂道」
東良美季(作家)
「──あれぇ、また一通かぁ。まいったな」
運転手の声で眼が覚めた。
白夜書房を出て早稲田通りで拾ったタクシーは、夜を切り裂いて走った。
ただ、渋谷を抜け恵比寿駅の手前で右に折れてからは、細かい道に入り、迷ったのか何度か角を曲がったようだった。僕は半分眠りながらシートに沈み込んでいた。
「ねえ、迎えに来て。会いたいの」と少し甘えたように言ったマリアの声が今でも耳に残っていた。
「迎えにって──」僕は暗い編集部の中で、疲労困憊した身体とまだ九〇パーセント以上眠ったままの頭のまま混乱していた。
「ねえ、マリア、どこにいるの? そもそも今何時だい?」
なんとか無理矢理そう言葉に出してみると、
「どこだって何時だっていいじゃない」と今度は怒ったように言った。
「会いたいのよ。迎えに来て」
タクシーは細い路地で何とかUターンを成功させ、元の通りに戻ろうとしているようだった。
「お客さん、悪いけど、ちょっと停まるね」
しばらく走ってから運転手はそう言って車を停め、ルームライトを点け、グローブボックスから地図を取り出したようだ。彼の手には僕が手渡したメモがあるはずだ。
暗く誰もいない白夜書房の編集部で僕が耳を当てていた受話器の向こうで、マリアはもう一度、
「会いたいの。迎えに来て」
とまるで独り言みたいに言った。そのときになって、僕は彼女が正体もなく酔っ払っていることに気づいた。
「マリア、すぐ行くよ。場所を言って」
「場所? 場所はねえ──、どこだっけ?」
舌がもつれた声が言う。背後で小さく古いジャズが流れていた。
「どこかお店にいるの? お店の名前は? 場所はどこ、家の近くなのかい? タクシーを飛ばしてすぐ行くよ。住所がわかるといいな」
答えはない。
「もしもし、マリア、聞いてる?」
「──わかんない」
そう言うと向こう側で「ガシャン!」と音がした。
「マリア、マリア!」
僕は大声で呼んだ。酔いつぶれて眠ってしまったのだろうか。このまま電話が切れてしまったら、もう二度と会えない気がした。だって、あの夜彼女のマンションの廊下でキスして渡辺海老蔵たちに見つかってから、約一〇カ月も連絡が取れなかったのだ。
「マリア、もしもし、マリア、マリア」
僕は彼女の名を呼び続けた。
「──あのね、お客さん」
人の良さそうな、中年の親切な運転手だった。
身体をひねって後部座席の僕に拡げた道路地図を見せた。
「今、この辺りだと思うんですよ」と指差す。
恵比寿駅から山手線の線路を渡り、目黒駅の手前。住宅街に入ったところだった。
「メモの住所はこの辺。だからすぐ先だと思うんだけど、どこも一方通行で入れないんだよね。ぐるっと大廻りするより、申し訳ないけどココで降りてもらって歩いた方が早いと思うんですよ」
僕はお礼を言ってお金を払い、住所の書かれたメモを握りしめて走った。
受話器に向かってマリアの名前を呼び続けてどのくらいたったろうか。あきらめかけたところで突然、
「すみません、お電話変わりました」と穏やかな声がした。店の人だった。僕は店の名前と住所を聞き、その場にあった原稿用紙に書きとめて白夜書房を飛び出したのだ。
タクシーを降りると蒸し暑い夏の夜だった。
木々の多い住宅街だった。それは「緑豊かな」というよりは「うっそうとした」と表現した方が正しく、しかも辺りはやけにに静かだった。不気味なほどに、と言ってもいい。
今、何時頃なんだろう? 腕時計を会社に忘れてきたのに気づいた。
もう夜中だろうし住宅街だということはあるのだが、それにしても静か過ぎた。奇妙なほどに人の気配がない。生きている人間がこの界隈にはいない──そんな気持ちにすらなった。マリアから電話がある前に見ていた夢、Kと一緒に訪れた湯島の街。人っ子ひとりいない、まるで人類全体が死に絶えてしまった世界のような、まだあの夢の中にいるような気がした。
タクシーの運転手が「この辺」と示した方向へ走った。車が一台やっと通れるような細い道だ。暗い先に、ポツンとひとつ立っている街灯、その光が照らし出している向こう側に違和感があった。
突然道が消えている。そう思った。
街灯の下へ辿り着いた僕は、
思わず「──ああッ」と声を上げた。
それは長い長い坂道だった。そして一歩を踏み出すのを躊躇するほど、急斜面の下りだ。走行する自動車の滑り止めのためだろう、アスファルトには蛸の吸盤を思わせる円形の穴が規則正しく、果てしなく彼方まで並んでいた。
あの坂だ。間違いない。
二年前、麹町のサン出版で首を言い渡されたあの日、原稿取りのため訪れたときに出くわした坂道だ。
思い出した。あのときも目黒駅から恵比寿方面に少し戻り、そして目黒川の方向へ向かって歩き、この坂道に出たのだ。ここはやはりマリアのマンションの近くなのだ。今まで僕は二度訪れているけれど、いつも目黒川から上り坂になっている路地を登った。今は逆の方面にいるのだろう。
下り始めると、さらにその尋常ではない急な勾配のほどがひしひしと感じられた。やはりあのときと同じだ。そう、まるでスキー場の上級者コースから滑り降りるような感じ。
そしてあの日は、事前に連絡を入れていたにも関わらず、坂の下に住んでいる挿絵画家はなぜか留守だったのだ。本当にマリアはこの近くのどこかにいるんだろうか? 二年前に挿絵画家がいなかったように、夢の中でKと訪れた出版社に誰もいなかったように、彼女もまた消えてしまうんじゃないか。
けれど坂道の中ほど、左手のうっそうとした森の中に、その店はあった。
ゆるやかにカーブを描く石畳の小径があり、その先に電気の消えた看板があった。店の前にはウッドデッキがあって、テラス席が作られている。三角屋根の建物。レストランのようだった。
入口は大きな一枚ガラスのドアで、太い真鍮のノブを押して入った。もう閉店しているらしく、灯りは半分以上落とされている。椅子がすべて逆さまになってテーブルの上に乗せられている。フロアの奥の方に、床にモップをかけている若い男がいた。長身で細身。白いワイシャツに黒のズボン、膝下まである長い前掛けをしている。僕に気づくと柔らかく微笑んだ。
長い髪を後で結んだ、端正な顔立ちの美少年だった。
どうやら、彼が電話で住所を教えてくれた人物のようだ。
「マリアさんですよね」と笑う。
そしてモップの柄を胸に置き、両の手のひらを合わせて頬につけ、小首を傾げるような仕草で、
「オヤスミ中です」と言った。
彼が合図を送るように眼を向けた先には、もうひとつ別のフロアがあるようだった。
そちらへ入ると、大きなテーブルが六つある中、窓ぎわの席にマリアは突っ伏して眠っていた。逆立てられたくしゃくしゃの髪を見たとき、どうしようもないほどの嬉しさがこみ上げた。脱色したのか夏の太陽のせいか、髪色は以前よりも茶色く、でもそのぶん輝いているようだった。
肩が剥き出しになった、足元まであるロングスカートの、眩しいほど鮮やかなグリーンのワンピースを着ていた。あらわになった腕から肩がよく陽に焼けていた。
その肩にソッと手のひらを置いた。その肌はひんやりとしていた。
「──マリア」
声をかけた。
「迎えに来たよ」
マリアはテーブルに突っ伏したまま、眼だけ開けて僕を見た。
「トーラさん、遅い」
すねたように言う。
「ごめん。これでも急いで来たんだよ」
そう言って隣の席に座ると、しなだれかかって僕の首に両腕を廻した。愛おしくてたまらなかった。
「会えてよかった」
強く抱きしめてそう言うと、
「それ、ちょっと大げさなんじゃない?」と笑った。
歩けないからオンブして帰ってというので、僕はマリアを背負って店の出口へ向かった。
掃除はもう終わったのだろう、カウンターの中に座っていた青年が立ち上がり、僕らをエスコートするようにドアを開けてくれた。
「お金を」と言うと、
「今度で大丈夫です」とにっこり笑う。
「表までお送りします」と一緒に外に出た。坂道へ向かって石畳の小径の小径を歩く。
マリアは僕の背中でまた眠ってしまったようだった。
「彼女、よく来るの?」
「常連さんです、それに──僕ら、お友だちでもあるんです」
僕は彼を見た。薄暗い外でも、やはり美しい顔立ちだった。
「僕、以前、歌舞伎町でホストやってたんです。そのときのお客さんです。まあ、あの頃はマリアさんって名前じゃなかったけど」
なるほどそういうことか。そう考えていると、不意に、
「大丈夫ですよ」と言った。
「──何が?」
「僕とマリアさん、そういう関係じゃないですから」
戸惑っていると、
「僕、ゲイなんです」と言った。
坂道を下りながら、「お気をつけて」という彼の声を聞いた。
振り返ると手を振っていた。僕も右手を挙げた。
滑り止めの穴の開いたアスファルトを下った。
「──重い?」
ほとんど眠ったままの声でマリアが訊いた。
「うん、重い」と答えると、僕の右耳をぎゅーっと引っ張った。
「ちゃんとオンブしてね。アナタには貸しががあるんですからね」
そう変に大人びた口調で言ったかと思うと、また眠ってしまったようだ。
「貸し」という言葉を考えた。初めて出会ったあの、歌舞伎町のぼったくり店を思い出す。何だかとてもとても昔、大昔の出来事ようだ。
坂の下まで残り五〇メートルほど。目黒川が見えたところで、「たぶんこの辺りだろう」と当たりを付けていた方向に、やはりマリアのマンションはあった。あの夜、渡辺海老蔵と一緒に歩いた路地を反対側から入り、エントランスを抜け、二階に上がった。
ドアの前まで来るとマリアはするりと僕の背中から下り、ワンピースのポケットから鍵を取り出してドアを開け、中に入っていった。
僕もついて入ると、ワンピースを肩から落として脱ぎ捨て、ショーツ一枚になった。彼女が身に付けていたのはそれだけだった。そして窓際のシングルベッドに敷いてあった、布団代わりのタオルケットを被って潜り込んだ。
部屋には常夜灯だろう、足元にひとつ、小さなライトがあった。見渡すと六畳ほどのワンルーム。家具はベッドと、細長い姿見しかなかった。窓には白いレースのカーテンがかけてあった。
「こっちへ来てよ」
タオルケットの中からマリアの声がした。
僕は服を脱ぎ、ベッドへ入った(続く)。
────
エリック・アンダースン「カム・トゥ・マイ・ベッドサイド」
Eric Andersen「Come To My Bedside」
https://www.youtube.com/watch?v=SLT-MjERhNQ