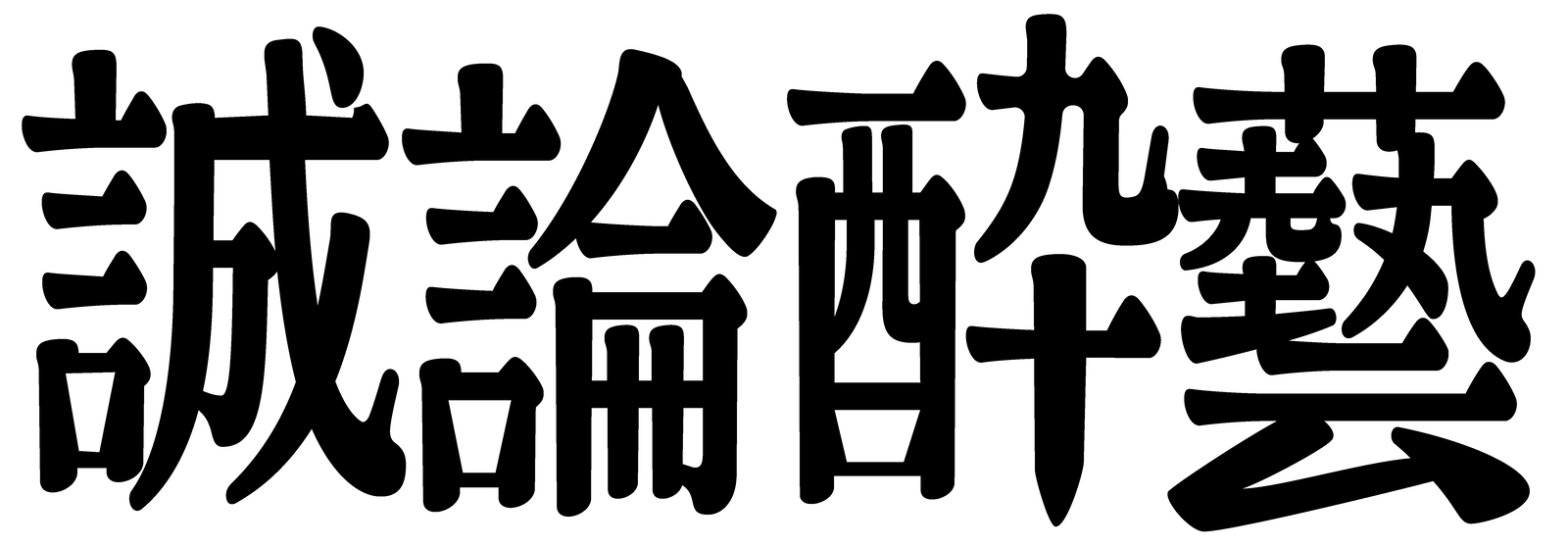おはようございます。ヨロンです。
ジリジリと焼けるような日差しにうんざりしている中、日韓のトラブルは収まる気配も見せず、韓国の狼狽ぶりが痛々しく感じられます。
合わせて、「あいちトリエンナーレ2019」での騒動は、表現の自由、右と左、そしてアートイベントというそれぞれの側から見ると、全く異なった風景が見えてきます。
芸術監督の津田大介さんはよく知っていますし、私としては彼がITや音楽系のコラムを書いていた頃のほうが馴染みがあるので、今回のイベント失敗に関しては、かなり違和感を持っています。と言っても、「太ったなあ」という違和感ではありません。
勝谷さんは、こういうときには話を外すことが多く、読者から「***について何で書かないんですか?」と意見が来ても、基本は無視でした。確信犯的に外していたからです。
おそらく今回のことを取り上げるとしたら、展示物に対する怒りを表しながら、脅迫でイベントを中止させようとする暴力を批判し、その批判に屈してしまった運営側をたしなめて、最後は産経と朝日の報じ方の違いを解説したことでしょう。
話題を外すのは、どのような書き方をしても、一方向から見ている人には納得がいかないため。彼は、左からは右翼と言われ、右からは左翼と言われ、果ては在日レッテルまで貼られることになって、右とか左とかの目で見られることを非常に嫌っていました。だから、右でも左でも、表面的なことしか言わない人とは距離を置いていました。
だからこそ、今回の件をどのように取り上げたのか、取り上げなかったのか興味がありますが、それは明日にでも。
今日は日曜日でもあるので、将来を考える話題を。何度か取り上げている話ですが。
国会では、重度障害者のふたりが登院したというニュースが流れていました。オリィ研究所の「分身ロボット」で遠隔地から参加するという可能性もありますが、そもそも「動かない体を替えてしまう」という発想も当然出てきます。
<触覚のある義手の開発に成功!そのリアルさは心も動かす>
https://www.gizmodo.jp/2019/07/scientists-have-created-a-prosthetic-arm.html
<手や腕と同時に触覚も失ってしまった人々は、これまで義手をつけても触覚を取り戻せないままでした。それが、このたびアメリカのユタ大学が開発した新しい義手を使えば、切断手術を受けた人も触覚を感じられるようになるそうなんです。
その義手の名は「LUKE」。もちろん、父との激闘の末に右手を失ったルーク・スカイウォーカーにちなんでいます。>
動かない体を動くパーツで置き換えていく。そして、脳がそれぞれを制御するという、まさにアンドロイドの誕生です。
<マイクロソフトがイーロン・マスク創業OpenAIに10億ドル出資、人類最後の発明に乗り出す>
https://www.gizmodo.jp/2019/07/microsoft-open-ai.html
<米マイクロソフトは、OpenAIに10億ドル(約1087億円)出資することを発表しました。
OpenAIは、2016年にイーロン・マスクが「Y Combinator」のCEOサム・アルトマンらと共に設立したアメリカのAI研究の非営利組織です。当初、IT業界の有名人などから10億ドルもの寄付を得て、設立されるなどして大きな注目を集めましたが、2018年2月に、イーロン・マスクは幹部職を退任しています。>
行き着く先は、人間の意識を機械にアップロードします。映画『トランセンデンス』が現実のものとなります。
<「20年後までに、人間の意識を機械にアップロードせよ」
東大発スタートアップは「不死」の世界を目指す>
https://wired.jp/series/away-from-animals-and-machines/chapter8-2/
<2019年3月に設立された「MinD in a Device」は
「20年後までに人間の意識を機械にアップロードする」というヴィジョンを掲げるスタートアップだ。
その共同創業者である渡辺正峰(東京大学大学院准教授)は
「機械に意識が宿る」と証明すべく、ラディカルな理論を打ち立てようとしている。>
以前、「乙武くんが世界記録を出す日」として、自分のブログに投稿したことを紹介しましたが、いずれパラリンピックで出される記録がオリンピックの記録を抜き、障害者の方が健常者よりも優れた身体能力を持つ日が来るでしょう。それまでには様々なハードルがありますが、方向性は変わりません。
乙武洋匡君に手と足が付き、通常の人間よりも高い身体能力を持つとどうなるのか。さらに彼の意識が人造人間に入ったとき、おそらく障害者に対する意識は変わります。しかし、新たな経済格差が生まれたり、年を取って精神的肉体的に障害を持つようになった健常者がどうなるのか、という問題も発生してきます。
目の前の障害や差別だけにとらわれていると、一方向の考え方に縛られがちですが、10年先、20年先に立場が逆転すると考えるだけで、見方は180度変わるのかもしれません。
新たなゲスト執筆者の登場です。
勝谷さんの仲間内では「M君」と言われている女性です。「M君」なのに名前が「沢木文」というのは、今回は突っ込まないようにします。
勝谷さんには優秀で個性的な編集者が何人か関わりましたが、彼女はその中でも特に優秀で信頼されていました。
私は、初めて会ったときのことを鮮明に覚えています。田舎から出てきたばかりの純な私は、月島の「殿下」邸で行われた飲み会に緊張して行ったとき、玄関に現れたM君を見て帰ろうかと思ったのでした。そんなことを書くと変な想像をされそうですが、そうではなく、「都会の女性ってこういうものかあ」と思ったのです。
しばらく離れていましたが、勝谷さんの通夜で久々に会って、その後機会があって、今回から寄稿をお願いしました。
どのような話題でも書ける人で、勝谷さんのエピソードもそれだけで本になるくらい持っているはずですが、今回は一回目なので自己紹介を書いてもらいました。今後は、この『××な日々。』には全く出てきそうも無い話題を取り上げていってもらおうかと考えています。
—– : —– : —– :
沢木文
Writer&Editor
1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』 『不倫女子のリアル』(ともに小学館新書)がある。
★勝谷さんとの関連性についての1回目
初めまして、フリーライターとして、活動している沢木文と申します。私は21歳から25歳くらいまで、勝谷さんのアシスタントをしていました。
あれは、2000年ごろ……勝谷さんに出会ったきっかけは、小学館から刊行されていたエクゼクティブのための男性向けファッション誌のインタビューでした。テーマは「個室風呂がある温泉旅館」。勝谷さんは当時、写真家の三好和義さんに師事して撮影を学び、「紀行家」という肩書でも活動していました。美しい文章と写真を、これまた品がいい女性ファッション誌『Oggi』(小学館)に連載していたのです。
私は足立区出身で、実家は土建屋。幼い頃より現場で働くアンちゃんたちから、色と欲にまつわるろくでもない知識を吹き込まれつつ、モツ煮や猫まんまを食べて育った下品な人間です。映画『翔んで埼玉』ではありませんが、そんな足立区出身の私が、千代田区番町に足を踏み入れるだけでなく、そこでオフィスを構える勝谷さんに会うのはドキドキものでした。しかも勝谷さんの文章は、教養があふれ、リズムがあり美しい。多くの編集者や文化人から「美文家」の称賛をほしいままにしていました。そんな私にとって、勝谷さんに会うのは、まさに雲の上の人に会うのも同然。
当時はインターネットも今ほど普及していませんから、勝谷さんの風貌は全くわかりません。私は文章から、白洲次郎のような眉目秀麗な美中年を勝手に想像。恐れつつもワクワクしながら、指定された番町のオフィスのエントランスに行きました。
すると、エントランスのソファにいたのは、丸顔の胡麻塩頭に、丸い色眼鏡をかけ、釣りのジャケットを着てエントランスに座っている、笑福亭鶴瓶師匠にどこか似ている中年男性。白洲次郎を想像して行ったら、鶴瓶が待っていた……あまりのイメージのギャップにのけぞりました。
そして「個室風呂がある温泉旅館」についてお話を伺うと、「エロい中年男が、お姉ちゃん連れ込んで、おま●こするところでしょ」と本質をズバッと言っていただき、何軒かの宿とおすすめのコメントをいただいて、インタビューが終了。その後、勝谷さんと私の猥談が盛り上がり、たまたま電話をかけてきた、編集者も合流して痛飲。人生初の二日酔いをした記憶があります。
その2週間後、アシスタントが必要だった勝谷さんから連絡があり、正式に荷物持ちになりました。仕事は月に1~2回、当時JTBの『旅』で連載していた全国の鉄道取材や酒蔵取材に同行すること。具体的な内容は、カメラバッグの運搬人と愛機・ペンタックス647のブローニーフィルムの交換。勝谷さんはフィルムが感光しないよう管理を徹底。撮り終わったフィルムの上下に黒いテープを留め、アルミの袋に入れるよう私に指示。当時、ファッション誌でも仕事をしていたのですが、そこまで用心深く管理するのは、後にも先にも勝谷さんしかいませんでした。
この連載は、後に『勝谷誠彦の地列車大作戦』(JTB)として書籍化されたのですが、本文中に「助手のM君」として出していただいたことも懐かしい思い出です。
勝谷さんと一緒に行動して気付いたのは、勝谷さんは、女性に対し、驚くほど優しく、腰が低く、紳士な態度を崩さないこと。しかし、権威を笠に着て威張る人には、手厳しい対応をしていました。勝谷さんは瞬時に人を見抜いて外さない。これは、大病院の長男に生まれ大人の手から手へ渡って育ち、週刊誌記者として海千山千を相手にしてきた経験から培われた「眼」なんだなと感じました。私に対しても、きっとお●んこ話の英才教育的環境で育ったことを見抜いていたのでしょう。
その後3年ほどで、勝谷さんはあっという間に有名になり、悠長に地方取材に行く余裕もなくなり、私のアシスタント仕事もなくなりました。それに伴い、書く内容の政治色も濃くなっていき、紀行家から、オピニオンリーダー的なコラムニストになりました。
テレビに活躍の場を移されてからは、数年に1回程度、仲間内の食事会などでお目にかかるようになったのですが、お会いするたびに、猥談と酒の話をしていました。結局、最後まで私と勝谷さんとの間に、おま●この気配すらありませんでした。
その理由のひとつは、勝谷さんの女性の好みが私と著しく外れていたこと。勝谷さんは、お嬢様育ちの女性が好きでした。上品で驕慢なのに弱く、色白で目が大きく、華奢な体型で、「アナタがいないと生きられない」という人を好んでいたように思います。誰もが美しいと思う女性のワガママに応えたり、そんな女性を追いかけて翻弄されることに喜びを感じていたのかもしれません。
そんな師匠・勝谷さんの名前を冠した本メールマガジンで、弟子の私が書かせていただくのは不思議な感じがします。勝谷さんとはさまざまな場所に行きましたが、どんな時もこのメールマガジンの前身である『さるさる日記』を書いていました。
通信状況が悪かったイスラエルからも高額な通信費をかけて更新しており、あの鬼神のような姿は今でも覚えています。
そんな師匠の弟子である私が書けるテーマは、最近の30~40代の女性のライフスタイルと、成功者の開運習慣などについて。これから、どうぞよろしくお願いいたします。